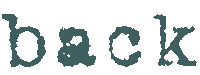恋の病にする薬
|
「三年五組、出席番号三十番、 高らかに読み上げられた自分の名に、矢萩豊は額を押さえた。一日の授業を終え、三階の教室を後にし、靴箱を目指していたときのことだった。 声の主を確認することもなくその場を去ろうとする豊に、その者はなお言った。 「おひつじ座、AB型。肩書きは一応生徒会長」 「一応って言うな、三年三組出席番号二十八番」 振り向かずに返すが、その声は遠ざかることなく、せわしい足音とともに豊についてくる。 「これは失敬。副会長の功績が大きいのを知っているものだから、つい」 豊は眉をしかめたが、言い返さなかった。目立つ機会が多いのは会長である豊であったが、現生徒会を支えているのが副会長の江坂であることは、彼が一番理解していた。 高い声は、ひきつづき豊の個人情報をひとつずつ明かしてゆく。 「得意科目は国語で、数学はそこそこ、一番の苦手は英語。好きな食べ物はコーンポタージュ。しかも自動販売機に入っている缶のものだというあたりが、なんともおもしろく――」 「うるさいな。ひとの嗜好をとやかく言うな」 耐え切れなくなって、豊は階段を降りたところで振り返った。豊より五段高い位置で足を止めた 一度も染めたことがない彼女の黒髪は、この高校では一番の長さだろう。左右の耳の上でくくってあるにもかかわらず、その先端はへそのあたりで揺れている。実乃里は夏服のセーラー服の上に白衣を羽織っていたが、袖も裾もだぶだぶで、ままごとかと言いたくなる出で立ちだ。 「それで、一体なんの用でしょうか、実乃里さん」 「よくぞ聞いてくれました」 そんな珍妙な格好でよくもそう偉そうに振舞えるものだ、と感心する豊の前で、実乃里はもったいぶるように二度うなずいた。 「うん、まあ、用といってもそうたいしたことではないのだけれど」 「たいしたことじゃないんだったら俺は帰るぞ」 「そんなに焦らないでよ豊くん」 先ほどフルネームを呼び捨てた彼女は、甘みを加えた声でそう言った。反して、豊が浮かべるのは苦笑いである。 「豊“くん”……ということは新作か」 「大当たり」 はしゃいで飛び上がろうとした実乃里だったが、階段の上であることを思い出しあわてて手摺りにつかまった。あぶない、あぶない、とつぶやきながら五段を駆け下り、豊のすぐ横に立った。 「落として割ったら元も子もないもんね。はい、というわけで、これ」 実乃里は白衣のポケットから小瓶を取り出すと、豊に差し出した。 「一気に飲んでくれるだけでいいから」 透明な瓶の中で、ほんのり薄桃に色づいた液体が揺れている。手を出すと了承したと取られかねないので、豊は小瓶を受け取らずに尋ねた。 「見たところラベルが貼っていないんですが」 「そりゃあ私の手作りで、非売品だからね」 「そうじゃなくて、なんの薬かと聞いているんだ」 「知りたい?」 にまりと笑った実乃里は白衣をなびかせくるりと回ると、「じゃーん」という効果音を口にした。 「ずばり、惚れ薬です」 「よくわかった。さよなら」 「ちょっと待ったちょっと待った。まだ飲んでないよ」 引きとめようと豊の前に回りこんだ実乃里に、豊は呆れ果てた。 「当たり前だ。誰が飲むか」 「ただの惚れ薬だよ」 「だからだろ」 突きつけるようにして持っている小瓶を指差し、豊は聞いた。 「効能は」 「飲んだ人が恋に落ちちゃいます」 「誰に恋するんですか?」 「私に恋するようにつくったから、私だね」 「ということは、この薬を俺が飲んだ場合?」 「私に恋に落ちます」 大きくため息をつく豊に、実乃里は笑顔を向けた。 「やったね、豊。これで豊は私に首ったけ」 あのなあ、と眉間にしわを強く刻み、豊は強く言い放った。 「いい加減にしろ。なんなんだよ、惚れ薬って」 「今言ったじゃない。飲んだ人が恋に落ちちゃう薬で、今回の場合、私に――」 「そういうことじゃない。部の管理体制はどうなっているのかと聞いているんだ。滝はなにしている。部長だろう」 「やだなあ、タキくんは関係ないでしょ。いや、関係あるか」 「今すぐ廃部にされたいか」 ご冗談を、と実乃里は冷や汗混じりに笑顔を浮かべた。 裏科学部、通称裏科。あやしげな薬の開発に力を注ぐ、奇怪な部活動である。入学して即入部を決めた実乃里は、最高学年になった現在、副部長を務めている。 「部長に無断で薬をつくったのはまずかったと思うけれど、研究熱心な部員を目の前にして、廃部はないんじゃないかな会長さん」 「つきあいの長い、長すぎると言ってもいい、俺とお前の仲だ。そりゃあ、力になってやりたいと思わないわけでもない。ないが、実乃里、約束したよな?」 はい、と実乃里は挙手をする。 「作品を豊に試してもらいたいときは、薬の効果を嘘なく豊に伝えること。その上で同意をもらえなかったなら、使用してはいけない。勝手に飲ませるなんてもってのほか。もしそんなことをすれば、縁を切る」 「その通り」 「だから今、同意をもらおうと奮闘しているんじゃない」 豊は肩を落とす。 「明らかに同意のもらえないものをつくるなというんだ」 「今までどんな薬も飲んでくれたじゃない。ネコ耳薬に、性別転換薬……」 「そういうことを大声で言うのはよしてもらえませんかね、実乃里さん」 豊は実乃里の白衣の襟を強くつかんだ。実乃里が今までにつくった薬は数知れず、そして、豊が実験台として貢献した回数もほぼ同数だ。だが、豊がふたつ返事で被験者になったことは一度もない。 「あれ、気にしていましたか」 「当たり前だ。五時間で効果が切れると言い張るから飲んだのに、一週間もネコ耳とおつきあいすることになったんだからな」 「江坂副会長に告白されるなんて夢は結局叶わなかったのに、ネコ耳には好かれてしまうんだねえ」 「売りたいというなら今すぐその喧嘩買おうか」 「まさかまさか。テスト期間中で、しかもテスト後に球技大会も控えていたために、帽子でネコ耳をかくして登校し続けた我らが生徒会長と喧嘩だなんて」 「……かと思えば、半日だと主張した薬は三十分で元通り」 「ワンピースを着た男子高校生が街中に出現というのは新鮮で、あれはあれでよかったんじゃないかな」 「よかったのはお前だけだろう、マッドサイエンティスト」 「あはは」 「言っとくが誉めてないからな」 けろりと応えない様子で、実乃里は自信たっぷりに言った。 「でも大丈夫だよ。この薬は三時間で切れるから」 「信じられるわけがないし、たとえ本当に効果が三時間だとしても、絶対に飲まん」 豊は実乃里をにらみつけた。 「実乃里さん。ちょっと聞きたいんだけど、君には、そう、確か彼氏がいるんじゃなかったっけ」 実乃里はにこりと自慢げに笑った。服装と言動は突飛だが、笑顔はけして悪くはないのが実乃里である。 「いますねえ、実にすてきな彼氏が」 「そして、俺には彼女がいるんじゃなかったっけ」 「ええ、ええ、そりゃもう。最近出来たばかりの、頭が良くてとびきりかわいらしい彼女が。無能な生徒会長と有能な副会長がくっついたって、それはもうこの学校の一大ニュース」 豊は頬を引きつらせ、「よくおわかりで」とつぶやいた。 「それでどうして俺が惚れ薬を飲むことになるのか、皆目検討がつかないんですが。俺に、頭が良くてとびきりかわいらしい彼女を裏切れと」 「話すと長くなるんだけど」 「学年上位の頭脳を以って簡潔に頼む」 「じゃあずばっと言うけど、こないだの金曜日に私、ラブレターもらったんだよ」 「……びっくりなこともあるもんだ。それで?」 「彼氏殿に見せたんだけど、へえ、の一言で終わっちゃったんだよね」 「だろうなあ」 目に浮かぶようだと言いたげに豊がうなずいた。 「確かに先に恋に落ちたのは私で、つきあってくださいとお願いしたのも私。だけど、つきあいはじめて一ヶ月」 ああ、と実乃里は大仰に叫んだ。 「もちろん、つれない態度や眼鏡の奥から向けられるクールな眼差しにときめきを見出しているわけだけれど。けれど、嫉妬してほしいという乙女心もわかってほしい……」 実乃里は示すように小瓶を自分の顔の横に持ち上げた。 「というわけでつくったのがこの薬。これを飲んだ豊が私に熱烈な愛をささやくことになれば、私のクールな彼氏殿もさすがに少しは思うところがあるんじゃないかな」 一通りの説明を終えた実乃里に、豊は釈然としない様子である。 「そういう性格だってわかった上でつきあっているんだろ。第一、反応がなかったからといって、嫉妬していないことにはならない」 「反応がほしいのが乙女心だよ」 負けじと実乃里も頬を膨らませて主張した。 「恋をすると欲張りになるの。全部かなえてなんて言わないけど、その中のささやかな望みくらいは満たされてもいいんじゃないかな。ハイダーリンと呼びかければ、ヘイハニーと返ってくるというような、そんな他愛もないこととか」 「時々俺はお前が心からわからないよ」 淋しいこと言わないで、と実乃里は顔をしかめた。 「でも、まあ、この際わからなくていいから飲んでよ。一生のお願い」 「そのせりふは聞き飽きた。お前には一生が何回あるんだ」 「じゃあ来世の分を前払い」 「そのせりふも聞き飽きた……実乃里」 豊がまっすぐに実乃里を見据え、名を呼んだ。 「俺が薬を飲めば解決すると、本気で思っているのか」 実乃里の動作がぴたりと止まる。強張った口から、実乃里は声を押し出した。 「どういうことかな」 「とぼけるな。どうして俺には飲ませようとする?」 答えない実乃里に、豊はさらに言った。 「薬の効果の割に使い方が回りくどすぎるんだよ。当初の目的の相手に飲ませなかった理由を言え」 実乃里はうつむいていたが、やがて、重い空気の塊とともに答えを吐き出した。 「それをすれば、終わりだと思ったんだもの」 「それに気づいているくせに俺に薬を飲ませようというのは、俺との関係がここで終わってもかまわないということだな。よくわかった」 ちがう、と実乃里が叫んだ。 「なにがちがうんだよ。薬で俺がお前に惚れて、たとえ三時間で効果が切れたとしても、その後も同じ関係でいられるとでも思っていたのか、お前は」 「豊だったら大丈夫だと思ったんだもの」 迷いのない声だった。 「つくった後で、とんでもないものつくっちゃったって気がついた。だから、本当は誰にも飲ませる気はなかった。だけど豊となら。薬が切れた後、多少時間は必要かもしれないけれど、あたしは、豊となら元通りの関係になれるって信じられた」 声を震わせて語る実乃里を、豊は黙って見下ろしていた。同じ背丈だったのはいつまでだったか、とそのようなことを思う。高校卒業まで一年を切っているというのに、実乃里の顔はどこか幼子のようで、時を感じさせない。 「実乃里。薬を貸せ」 豊の意図もわからぬまま、実乃里は素直に小瓶を差し出していた。豊の穏やかな様子に安心していたのかもしれない。 しかし、小瓶を受け取った途端、豊の顔から表情が消えた。 「廃棄決定。窓からさようなら」 開け放たれている廊下の窓に向かって振りかぶる。実乃里は悲鳴を上げて豊にしがみついた。 「やめて投げないで。作品はどんなでも、子どもみたいなものなんだから。タキくんだって、いつもそう言っているんだから」 「子どもだって言うならこんな使い方するな」 動作を止めた豊が語気を強めると、実乃里は目を見開いた。その顔が、直後、くしゃりとゆがむ。 めんどうくさい、という感情だけがわきあがるのならば豊もむしろ楽かもしれない。相手のことを知りすぎているがゆえに、やりづらくてしようがなかった。豊は片方の手を実乃里の頭の上でぽんぽんと弾ませた。実乃里はふにゃふにゃの声を上げて泣き出した。 「おい。高校生とは思えない泣き方だぞ」 「豊が頭撫でるからだもの。泣くつもりなかったのに」 「これは叩いているんだ」 豊はため息をついた。できるだけ口調をやわらかくしようと努める。 「お前、さっき打ち明けた不満のひとかけらでも、直接訴えたか。訴えてないだろう」 「だって、口うるさいと、かわいくない彼女だと思われるじゃない」 「黙々と惚れ薬完成させる方がよっぽど恐ろしい彼女だ。お前のその脅威の積極性は、どうして変な方向にばかり働くんだ。ハイダーリンは言えるくせに肝心なことは言わない」 惚れ薬をつくる暇があったら直接喧嘩でもふっかけろ、と豊は言った。 「お前は今まで変な薬をいっぱいつくったけど、こんな薬には頼らずに、努力して、告白して、承諾もらって、彼女になったんだろ。すてきな彼氏殿だと言うんだったら、そのすてきな彼氏殿をもっと信用しろ。喧嘩ひとつで終わるようなら、その程度のつまらない男だったということだ。それならさっさと終わっておいた方が、得だ」 豊のシャツを涙で濡らしていた実乃里が、突如小さなこぶしで殴りかかってきた。 「なんだよ」 「訂正して。いっぱいつくったけど、変な薬じゃないもの」 しゃくりあげながらも、強い口調だった。 「喧嘩ひとつで終わりたくなんかないけど、もし終わったとしてもつまらない男なんかじゃないもの。私が悪いだけだもの。タキくんはつまらない男なんかじゃない。訂正して」 「わかったわかった。その点は悪かった、謝るから」 手を止めた実乃里をやれやれと豊は見下ろした。 「ほら」 小瓶を実乃里の前に突き出した。むすりとした顔のままで、実乃里はそれをそっと受け取る。 「こんなものをつくってしまうくらい思いつめていた、とでも言って来い。全部ぶちまけろ。その後でお前が責任を持って廃棄しろ」 示すように、豊が廊下の先を見た。実乃里もその視線に誘導され、同じ方向に目をやった。ここからは遠く、その扉もぼんやりとしか見えない。 実乃里は手の中の小瓶を握り締めると、見つめる方へ二歩踏み出した。しかしそこで立ち止まると、不安そうな目を豊に向けた。 「ついていかないからな。部室の前までというのも却下だ」 実乃里が眉をつり上げ、不満げに目を怒らせる。 「どけち」 「あほう、いい加減自立しろ。靴箱で江坂が待っているんだよ」 豊は腕時計を見て、眉をしかめた。すでに随分な遅刻だ。 「なんであんな頭いい子が豊を好きなんだろう」 「俺も同じ質問を滝にしてみたいよ」 「ほんとだね」 予想に反して、どこか悲しげな声が返ってきた。 「なんでタキくん、私が告白したとき、いいよって言ってくれたんだろう」 豊は嘆息する。 「これ以上変なことに巻き込まれたくないから言うけど、滝がお前のこと好きになったのって、一年の夏だぞ。お前が好きになるより、ずっと前」 実乃里はぽかんとした。 「うそ。聞いたことないよ、そんなこと」 「あのつれなくて眼鏡でクールな裏科学部部長が言うわけないだろう。本人は無表情のまま、シャイだから、なんてぬかしていたが」 実乃里はしばらく口をぱくぱくさせていたが、やがて、早口に言った。 「それが本当なら、どうして豊はそれを今までおしえてくれなかったの」 「あんなのでも一応友人だからな。三年間クラス一緒だし」 「あんなの、とか言わないで」 「はいはい」 靴箱の方向に歩き出す豊に、実乃里は言った。 「豊に飲ませようと思ったのは、豊なら三時間以上効くはずがないって安心できたからだよ」 振り返る気はなかったのに、豊は足を止めてしまっていた。 「江坂さんに告白する勇気がなくて、二年間もぐずぐず情けなく片思いして、それでも諦めないで、結局恋を実らせた豊だもの。いくら私の薬でも、三時間も私に惚れるはずがない」 「悪かったな二年間もぐずぐず情けなくて」 くすりと笑い、実乃里は、ごめんね豊、と謝った。幼さの消え失せた、初めて見るような顔だった。気がつけば、別にいいよ、と豊は答えている。 「自分でも情けないってわかっているし」 そう付け足して豊が再び歩き出すと、背後でまた実乃里が笑む気配がした。 実乃里が、ねえ豊、と呼びかける。 「まだなにかあるのか。さっさと行けよ」 「氏も育ちも同じのくせして、私たちって全然似てないよね」 今度は足を止めることもなく、豊は言った。 「二卵性だからな。こんなもんだろ」 |