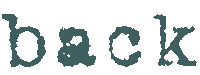世界の中心
|
もしかするとあなたは、大げさな、と笑われるかもしれません。しかし、少しも大げさな話ではないのです。 世間のことさえよくわかっていない、龍彦のようなものが「世界」などという語を使うことは、恥ずかしいことかもしれません。しかし、思い上がっているつもりは、龍彦にはありません。ただ、龍彦はお嬢が大切で、お嬢がそばにいてくれるだけで、満たされるのです。龍彦の世界の中心はお嬢ですが、お嬢の世界の中心が龍彦でなくたって、龍彦はいっこうにかまわないのです。 もちろん龍彦には、そのような思いをお嬢に告げることはできません。思いを抱いていることさえ、身に余ることのように感じます。けれど、お嬢は、龍彦の手を握り、にっこり笑ってこう言うのです。 「龍彦と遊ぶのが一番楽しいわ」 その言葉を耳にすると、思いを伝えることは叶わなくとも、抱いていることくらいは許されるのではないかと、そのような心地が龍彦にはするのです。お嬢の笑顔はまぶしくて、それを見るだけで、龍彦は本当に嬉しいのです。 「 青年の声に、お嬢は答えません。声変わりが始まった頃などは、声を出すたびに「つぶれた蛙のようだ」と彼を笑ったお嬢ですが、なにしろ声音が変わりきってもう数年です。今更声の調子だけで笑いが混み上げるはずもなく、お嬢は口を閉ざしています。 背も、今ではお嬢と彼は、頭ふたつは違います。「前は小さいことを家中のものにからかわれていたというのに、あんなに伸びるなんて、おかしいわ」と、いつかお嬢は不満そうでした。今もお嬢は、その日と似たむくれ顔をしていましたが、もちろん、今更身長についてとやかく言っているわけではありません。座布団に座るお嬢の前に置かれているのは、昼の膳です。お嬢はこのところ、食事のときはあまり機嫌がよくありません。 「柳さま。また、ごはんを残しましたね」 彼にこう言われることが、わかっているからです。 「おなかがいっぱいなのだもの」 一度箸を置いてしまうと、お嬢は再びそれを手に取ることはありません。「もっと食べるべきだ」とつくづく龍彦は思うのですが、お嬢は両の手の平を膝の上でかたくこぶしにして、その気がないことを示しています。 「あと一口ずつ、召し上がりませんか」 彼がそう言っても、お嬢はがんとしてつっぱねます。 「いや」 しかし、ため息をつきながら彼が膳を下げてしまうと、お嬢は不機嫌な顔を早々とおしまいにし、「あそぼう」と龍彦に手を伸ばします。着物の腕から覗く手首が、白く、折れそうです。来月、十三になるとは思えない、細い手首です。 お嬢が遊ぶとき、龍彦はいつもお嬢のそばにいます。今でも、遊びに加わることが少なくありません。何をして遊ぶかということはいつもお嬢が決めました。龍彦はそれでかまいません。何をするかということを、お嬢が時間をかけて悩むということはありませんでしたし、お嬢が選んだものが、お嬢が一番楽しめることだと龍彦は疑わなかったのです。 幼い頃は、よくままごとをしました。龍彦が小さくとも、お嬢は龍彦に赤子の役を与えるなどという、そんなひどいことは一度もしませんでした。「龍彦、わたしをお義姉さまと呼ぶのよ」と、今よりずっとぷくりとした頬で笑っていました。台所からいただいた、淵の欠けた茶碗や小鉢に、たんぽぽの葉などきれいに盛りつけ、龍彦たちの前に置いたものです。お嬢は実に料理上手でありました。夫役の少年に料理の腕前を誉められると、お嬢は「いずれ母さまのようになるのですもの」と言いました。お嬢の母親は、自ら台所に立つ珍しい方でした。 「龍彦。赤いのは苺なのよ。間違っても、にんじんじゃあないわ」 二月ほど前から、お嬢はまたままごとをするようになりました。以前は、本を読んだり買い物にでかけたりということを彼としていたのですが、それらをお嬢はぱったりやめてしまったのです。天気に関係なく、お嬢の「あそぼう」は部屋の中限定となっていました。 茶碗の中身はお手玉やおはじきや、色紙の細かく切ったものです。今もお嬢は、鋏をちょきちょきちょきと動かして、赤い色紙を小さな四角にしていきます。畳に落ちた赤い四角は、少しゆがんだように見えます。 お嬢は今では、庭にさえ出ません。 「龍彦、できたわ。おいしそうでしょう?」 最近のままごとでは、龍彦はお嬢の「友人」の役です。お嬢は龍彦に、「お義姉さまと呼びなさい」とは、もう言いません。 「龍彦。龍彦はどこなの」 お嬢の呼ぶ声に、彼は庭から答えます。 「ここですよ」 ふすまが開け放たれているため、庭からは縁側に最も近い部屋、そしてその奥の部屋まで見通すことができます。縁側に近い部屋に差し込む日の光さえ嫌うように、お嬢は奥の部屋から縁側にいる龍彦を見つめました。 「どうしてそんなところにいるのよ」 「見てわかりませんか。洗濯物を干しているのです」 「そんなことを聞いているのじゃあないわ」 「柳さまのお手玉も人形も、日にさらさないと虫がわきますよ」 縁側に並べられたお手玉は、ぽつりぽつりと、花が咲いたように鮮やかです。いい天気です、と彼はお嬢に背を向けたままつぶやきます。 「どうしたのです、龍彦をさがしに来たのでしょう。こちらへ来ればいいじゃないですか」 お嬢がしかめつらをしているのが、龍彦には見なくてもわかります。お嬢はゆっくりと歩いてきましたが、縁側の板の上には足をおろさず、部屋の畳のところから龍彦に手を伸ばしました。龍彦の服の端をにぎりしめ、引っ張ります。 いい天気です、とまた彼がつぶやきました。 「外に出ませんか。いつかのように、町に買い物にでも」 お嬢は答えません。龍彦を引っ張って足早に部屋の奥へ戻っていきます。 龍彦は、自分の名前が気に入っています。最近は特に、三日に一度はお嬢が誉めてくれるからです。 「いい名前でしょう。誇りに思いなさい、龍彦」 お嬢の目はきらきらしています。龍という生き物がとても好きだと、お嬢は言います。 「龍は天を翔けることができるのよ」 もちろん、龍彦にそのようなことはできません。しかし、お嬢がそう言うと、そのようなことも可能なのではないかと、ちらりとですが、思ってしまいます。 「柳はリュウとも読むでしょう」 お嬢は畳に「柳」と細い指で記します。「わたしの名前とも繋がっているのよ」と、お嬢は語ります。それからぽつりとお嬢は洩らします。 「柳という名は、母さまがつけたのよ。だけど、少し大層に過ぎる名前だわ。柳だなんて」 何も言葉を返せないでいる龍彦に、突然お嬢が言いました。 「龍彦、髪が伸びたのじゃあない? 切ってあげるわ」 とんでもない、と龍彦は思いましたが、お嬢はすぐさま鋏を取りに行ってしまいました。鋏を手に戻ってきたお嬢は、ほほえんでいました。 いつだったか、夏の日、お嬢の母親が「柳の笑顔はひまわりのようね」と誉めたことがありました。嬉しかったのでしょう、お嬢の顔が、さらに輝いたことを龍彦はよく覚えています。この家のものが弱いのは、お嬢の母親の笑顔、そしてお嬢の笑顔でした。龍彦もすでに、「お嬢が楽しいのならば髪を切られるのも悪くはないかもしれない」と感じるようになっていました。それに大体、お嬢に逆らうことなど、龍彦にできるはずがないのです。 「かっこよくなるわよ」 お嬢は鼻歌とともに、軽快に鋏を動かします。お嬢の体からふわりと、線香の香りがしました。 散髪が終わったのは、日が傾き始めたころでした。お嬢が切った龍彦の黒い髪が、新聞紙の上にちらばっています。 できた、と言ったお嬢は、疲れたのか、今は畳で大の字になっています。切っているときは随分真剣な様子でした。 「なんだか、眠くなってしまったわ」 そのままお嬢はうとうととしはじめました。鋏は、刃が開いたまま新聞紙の上に無造作に置かれています。 やがて、お嬢の細い寝息が聞こえてきます。それを耳にすると、龍彦はほっとします。 彼は洗濯物を取り込んだ後で、お嬢の眠る部屋にやってくると、お嬢を寝床に運び、新聞紙や鋏といったものを片づけました。 「やっぱり、短い方がずっといいわ」 龍彦の髪の毛をつまみながら、お嬢は朝からひどく嬉しそうです。どうやらお嬢からすると会心の出来であるらしいのですが、お嬢以外はそうは感じないようです。龍彦の変化に気がついた家のものは皆、「お嬢が切ったのですか」と気の毒そうな目を向けてきます。 「正直、切らない方がよかったと思いますよ」 彼も、お嬢に言いました。お嬢は、ぷいと横を向いてしまいます。 「これでいいのよ」 確認するかのように、お嬢は龍彦の髪をつまんだりひっぱったりかきまわしたりしています。そんなお嬢を見上げながら、胸が痛むのを感じましたが、龍彦にはその思いの正体が咄嗟にわかりませんでした。 「柳さまもそろそろ髪を切るべきではないですか」 お嬢は手を止めました。そのようなことを言った口が心底にくたらしいというふうに、お嬢は彼をじっとにらみあげています。お嬢の顔を見ながら、ああそうだ、お嬢にそう伝えたかったのだ、と龍彦は思いました。 「あっちへ行って頂戴」 お嬢は冷たい声で言い放ちます。お嬢の強い瞳は、うるむのをじっと耐えているようにも見えます。 「外に行きませんか」 「またそんなことを言いに来たの。いやよ、行かないわ」 「なぜです」 「外はまぶしいもの」 「ずっと部屋で人形遊びなどしているからです」 ため息混じりに彼は言います。 「それではいつまで経ってもまぶしいままですよ。少しずつ、慣らしてゆかなくては」 「慣らしてどうするのよ」 「そうしなければ、一生外に行けなくなりますよ」 「かまわないわ」 「柳さま」 穏やかな声でしたが、お嬢は一瞬びくりとしました。それでも、動こうとはしません。お嬢は拒絶するように、彼から目をそらしました。龍彦は無性に悲しくなります。 これ以上言っても無駄であることは明らかで、そうなると彼にはその場を去ることしかできることはありません。彼は幾度か振り返りますが、足音が遠くなるまで、お嬢は微動だにしません。 その日も彼が、昼の膳を運んできました。お嬢の身の回りの大体のことは、すべて彼がやることになっています。いつもと違うことと言えば、一緒に女がお嬢の部屋を訪れたことです。料理をつくっている、たえという中年の女です。 「柳嬢さま。今日は、しっかりとお食べになってくださいね」 食べる前からそのような口出しをされて、お嬢はいっそう不機嫌そうです。お嬢は龍彦を見つめ、言います。 「なあに、龍彦。あなたも食べろって言うの」 わずかでも多く食べてほしい、というのは龍彦も願っていることです。しかし、悲しいことに、龍彦の思いはお嬢には届かないようです。半分も口にせず、お嬢は箸を置いてしまいます。 「おいしくないのですもの」 彼はただじっと、お嬢の青白い顔を見つめます。 「龍彦はすきよ。だって、龍彦は余計なことは言わないんですもの」 折り紙にもお手玉にもままごとにも飽きたお嬢は、龍彦の隣で畳に横たわっています。畳には、いかほどの重さがかかっているのでしょう。風が吹くとお嬢は舞い上がるのではないか、と龍彦は心配になりますが、ふすまを閉じた部屋の中では、そのようなものは吹きません。紙のように白い、お嬢の肌。 「龍彦はすき」 歌うようにお嬢は言い、そしてつぶやきました。 「…… そのままお嬢は眠りに落ちていってしまいます。 お嬢が昼寝をすると、龍彦はいつも少し安心します。昼間は、お嬢はうなされることはありません。 彼がふすまをすらりと開くと、薄暗い部屋の中に、午後の淡い光が入り込んできます。彼は用意した寝床に、小さなお嬢を抱え上げて連れて行きました。 お嬢のいなくなった畳の部屋には、お手玉やおはじき、大小さまざまの人形、色紙が散らばっています。戻ってきた彼はそれを静かに見下ろしていたかと思うと、それらのひとつひとつを手に取り、片づけ始めました。てきぱきと動いていた彼でしたが、やがて手を止めました。小さな着物を身に着けた、木で出来た体を、両手で包むようにして持ち上げます。 ちょうどそのとき、名を呼ばれ、彼は振り返りました。 「何をしているのですか」 開いたふすまの向こうでそう尋ねたのは、たえでした。たえは龍彦を見ると、ああ、と言いました。ここ二月で、頬の肉が落ちたたえは、ぐっと老け込んだように見えます。 「柳嬢さまの、人形ですか。確か、絳時さまが差し上げたものでしたよね」 「ええ」 何か用でしょうか、と彼が尋ねると、たえは苦しそうに眉をゆがめました。 「近頃、柳嬢さまはますますお食べにならないのです」 「……わかっています」 答える声は、ひどく悩ましげに、低く響きます。たえは、一体どうしたらいいのでしょう、と言いました。 「亡くなられて、もう二月になります。一時は、立ち直られたかと思えたのに。このままでは、柳嬢さまが」 お嬢が、と考え、龍彦は胸がひやりとします。 たえの声を遮るように、彼は言います。 「わかっています。わかっているんです」 たえは口をつぐんでいましたが、やがて、つくり上げたような明るい声で言いました。 「その人形、柳嬢さまのところへ持っていくのですか」 「ええ。柳さまは、勝手に床に運んだことは怒らなくても、そばにこれがないと怒りますから」 たえは、淋しげな笑みを浮かべました。 「絳時なんて大きらい、とおっしゃるのに、柳嬢さまはこの人形を離さないのですね」 「逆でしょう」 たえは不思議そうな顔をしましたが、彼がそれ以上言わないようなので、頭を下げてその場を離れてゆきました。たえの目元が、赤く腫れているのを、龍彦は見ました。たえも、お嬢を大切に思う一人なのでしょう。 しばらく、彼はその場に立ちすくんだままでした。ぽつりと、言いました。 「……きらいであるほど、これに執着するのです」 龍彦は、無表情とも言える、目の前の白い顔をじっと見つめました。世界のすべてを呪ってしまいたいと言いたげな、黒の瞳をしています。口はやわらかく閉じられているだけでしたが、そこには、純度の高い苦しみがちらりちらりと垣間見えるようでした。そのような顔には美しさすら感じることができるかもしれません。しかし、あたたかみといったものからは、ひどく遠いように思われました。 もっとも、龍彦も、自分の顔にあたたかみなどというものがあるとは思いません。目の前の顔は、まるで鏡です。彼は、問いかけました。 「柳さまをこのままにしておいていいのか」 そして、「いいわけないだろう」と、自分で答えました。歯を噛みしめる彼は、涙をこらえているのでした。 やがて、彼はお嬢の眠る部屋へと歩き出します。彼はつぶやきました。 「柳さまの望むものと、柳さまの幸福が、同じところにあるのならよかったのに」 小さな声でした。彼はつくりものの体を、温度のあるお嬢の体の隣にそっと横たえました。 お嬢は寝言で小さく「絳時」と呼びました。龍彦は、自分の無力さをこのときほどくやしく思ったことはありませんでした。 いつもの夕餉の時刻より幾らか遅れて、お嬢は目を覚ましました。自分が布団の中にいることに気がついたお嬢は、そばに龍彦がいるのを見つけて、ふわりとほほえみました。母親に似た、見るものに幸福を与える笑顔です。しかし、お嬢の笑顔を見ると龍彦は胸が痛みました。お嬢は最近、龍彦にしか笑いかけないことを龍彦は知っています。 「龍彦」 お嬢は龍彦を呼びます。 「わたしはあなたがいればいいわ。絳時とちがって、あなたはやさしいもの。ずっとそばにいてくれるでしょう? それだけでいいわ」 声が細いのは、寝起きだからなのでしょうか。それだけであってほしいと龍彦は願います。 「兄弟なのに、似てないこと!」 お嬢はくすくす笑います。 次の日は、朝から雨が降っていました。 「雨ですよ」 知っているわ、とお嬢はどこかそっけない調子で答えます。 「音が聞こえるもの」 「でかけましょう。雨だから、まぶしくはありませんよ」 彼はそれが言いたかったようです。静かにほほえんでいますが、お嬢は首を力なく横に振りました。 「濡れるもの」 「傘を差して行きましょう。なんなら、庭に降りるだけでも」 「行かないわ!」 お嬢は強く叫びました。 「どこにも行かない! 外になんか出たくないって、言っているじゃあない」 龍彦にしがみついて、わっと泣き出したお嬢を、彼は苦しげな目で見下ろします。 「あなたはどうしてそんなことを言うの。龍彦はやさしいのに。とてもとても、やさしいのに!」 彼は静かに言いました。 「やさしくなんか、ないんですよ。本当は」 「いいえ、やさしいわ。絳時なんかより、ずっとずっとやさしいわ」 彼はお嬢の髪を撫でます。柳さま、と呼びかけます。しばらく切っていないお嬢の髪の毛は、重く、指にからまるようです。 「さわらないで頂戴。ええ、さわらないで。やさしくないのならさわらないで」 龍彦を抱きしめたまま、そのようなことをお嬢は涙声で訴えます。 「出てって。わたしにかまわないで。もう、この家から出て行きなさい」 「私をどうこうできるのは、旦那さまです。そういうことは旦那さまにおっしゃってもらわなければ。もっとも、お忙しい方ですから、しばらくは戻られないでしょうが……。旦那さまから命じられれば、今すぐにでも私はここを出て行きますよ」 はっとお嬢は顔を上げ、問いました。 「出て行きたいの」 「そんなことは言っていませんよ」 そう、とお嬢は喉の奥で言いました。 「父さまも帰られないし、母さまもいない。母さま、母さま……」 「柳さまがそのようでは、奥方さまも心配します」 「わかったようなことを言わないで。心配だと言うのなら、どうして母さまは来ないの」 彼は顔をゆがめました。 「いつまでそうなさるおつもりですか」 「聞きたくないわ。聞きたくない」 その日のお嬢は、おつゆを三口ばかり飲んだだけで、他のものは何も口にしませんでした。おかゆをつくりましょうか、それとも甘いものなら食べますか、と彼が尋ねましたが、お嬢はいらないと言いました。 「横になった方がいいのではないですか」 それもいらないと言い、お嬢は、壁に背を預けて一日ぼんやりとしていました。 「何か用なの」 ふすまを開けたところに、彼が立っています。この日も壁際にいたお嬢は、龍彦を見ながら言いました。 「食べなさい、と、出かけましょう、ならもう言わないで」 「お墓に行きませんか」 お嬢の瞳が震えました。 「なんですって?」 「お墓参りをしましょうと、言ったんです」 お嬢は強く首を横に振りました。黒い髪が、ばさりと揺れました。 「行かない。必要ないわ。仏壇にお線香をあげているもの」 「ですが」 「行かない!」 わかりました、と静かに彼は答えました。そのまま去るかと思われた彼は、しかし、部屋に入ってくると、お嬢の目の前で足を止めました。彼と壁に挟まれる格好になったお嬢は、彼を見上げます。 お嬢がおびえているのが、龍彦には感じられます。なによ、と力なくお嬢は言いました。 「本当は、こんなことは……いえ、何も言いません」 思えば、現れたときから彼の目つきは異なっていました。この日、お嬢が彼の誘いに乗らなければと、決意していたのでしょう。 彼は手を伸ばしました。お嬢は思わず目をつぶり、怖さゆえに、強くしがみつくように龍彦を抱きしめました。 お嬢に手を伸ばしたのではない、とお嬢が気がついたのは、龍彦がお嬢から離れた後でした。お嬢は叫びました。 「何をするの。返して」 見開いたお嬢の目は、なんと痛々しいのでしょう。 「このような人形に執着しているから、いけないのです」 「龍彦!」 彼はお嬢に背を向けると、部屋を後にします。はっとお嬢が息を呑むのがわかりました。煙のにおいがします。 「やめて!」 お嬢は叫びながら駆けてきます。しかしもう彼は、縁側から庭に降り立っていました。彼は庭の焚き火の中に、お嬢から奪い取った、作り物の小さな体を投げ込みました。 お嬢の悲鳴が響いています。 「何をするの、何をするの、何をするの! 龍彦! 離して頂戴、ああ、龍彦!」 「もうやめてください!」 おそらく、駆け寄ろうとするお嬢を、彼が体で制しているのでしょう。そんなに大きな声を出して、お嬢が倒れてしまわないか龍彦は心配です。放り投げられたときの白い衝撃が徐々に薄らぎ、ぱちりと火のはぜる音を耳にすれば、ようやく熱いということを龍彦は感じました。不恰好に短い髪の毛にも、すでに火がついています。 「絳時が言ったのだわ。絳時が、弟だと」 「ええ、言いました」 「なのに、殺すの。あなたが弟を殺すのだわ。絳時が言ったのに! 絳時が、龍彦は弟だと、言ったのに!」 「そうです。この絳時が、私の弟とでも思ってくださいと、あれを柳さまに差し上げました。柳さまがあれに名をつけ、たいそう大切になさっていたことを、嬉しく思っていました」 「ならどうして。わたしは龍彦を大事にしたのに。そうよ、絳時なんかよりずっと大事にしたわ」 「嬉しく思っていました、あの方が亡くなられるまでは。……あなたは、龍彦以外を見なくなった」 だって、とお嬢の声が聞こえます。炎に遮られ、龍彦にはお嬢の姿は見えませんでしたが、お嬢の声は、今にも泣き出しそうに掠れていました。 「絳時はわたしにやさしかったわ。わたしにいっとうやさしかったのに、なのに、母さまがいなくなって冷たくなったわ」 「確かに、柳さまの望むとおりにはしなかったでしょう。しかし、何もせずにいられますか。食事も取らない、日にも当たらない。奥方さまの後を追うような行為を、どうして見過ごせるのです。人形にだけ笑いかける柳さまを、絳時は見ていられません」 「人形だなんて言わないで頂戴。あなたの弟だって、言ったじゃあないの。大切にしてやってくれと、言っていたじゃあないの……」 「ご自身のことをおろそかにしろとは言いませんでした!」 身を削っているかのような、声でした。彼の叫びに答えるかのように、風がごおっと炎を煽りました。 「いや、母さま! 龍彦!」 お嬢が泣いています。彼がお嬢を、抱きしめているようです。 「やさしい方でした。家のものは皆、奥方さまが大好きでした。この上、柳さまもいなくなるつもりなのですか。柳さままで」 やめて、とお嬢が叫びます。 「柳なんてきらい。きらいよ。強くしなやかになんて、なれないもの。どうやったって、その名のようには、わたしは生きられないのだもの」 「絳時がおります。絳時が」 「絳時はきらい。大きらい」 「かまいません」 いつしか、彼の声にも涙が混じっています。 「なぜこんなに細くなってしまったのです。柳さま……お願いです。絳時をきらいでかまいませんから、食事をしてください。部屋の外にも、出てきてください……」 身を焼かれながら、龍彦はどこか、ほっとしたような気持ちになっていました。二月前、お嬢の母親はこの世を去りました。うつり病であったため、母親が臥せってからは、お嬢は母親に会うことができませんでした。母親を失ったお嬢は、夜、よくうなされて目を覚まし、龍彦を抱きしめて泣きました。お嬢をなぐさめるための、自由になる声と体がないことが、龍彦はずっと悲しくてなりませんでした。 炎の中で、思います。お嬢は、彼の元で泣くべきだったのです。 お嬢、絳時の顔を見てください。ここのところあなたは、睨むようにしか彼を見ていませんでしたが、彼の顔が二月前とはまるで違うことに、気がついていましたか。頬がこけているのも、今にも倒れてしまいそうに青白いのも、お嬢、誰を思う故なのか、わかっていますか。 お嬢がしゃくりあげています。 「煙、煙。煙が昇っていく。白い煙が。龍彦、龍彦もわたしを置いていってしまうの」 「絳時がおります。そばにいます。絳時だけでなく、旦那様も、たえも、他のものも。皆、柳さまを大切に思っています」 「……絳時」 お嬢が細い声で尋ねました。 「龍彦は、龍になるの」 彼はそれには答えず、言いました。 「……どうか、柳さまも、柳のように。今でなくとも」 お嬢が、赤子のように声を上げて泣き出しました。二月前から、お嬢が龍彦以外の前で泣くことは、初めてでした。今だけは彼とともに泣いてほしい、と龍彦は思います。そして、できることなら明日か、明後日か、お嬢がまた笑ってはくれないでしょうか。龍彦は、お嬢の笑顔が心から好きだと思うのです。 幸せでした。いつもお嬢が、龍彦のそばにいてくれました。それが、この人形の身に、どれほど特別で嬉しいことだったか、お嬢、あなたにはわかるでしょうか。 お嬢、龍彦は、お嬢といっしょで、本当によかったと思うのです。 意識は昇るようであるのに、視界ははっきりしません。煙には、目というものはないのでしょうか。でも、お嬢の声はよく聞こえます。お嬢がどこにいるのかも、ぼんやりとですが、わかります。まだ、泣いているのですか。 お嬢、龍彦は、空に溶けます。以前、お嬢が龍彦を抱えて、絳時と町のあちこちを歩いたことがありましたが、風に運ばれれば、龍彦はあのときよりずっと遠くに行くのでしょう。 しかし、どんなに広い世界を感じようと、ああ、お嬢、龍彦の世界の中心は、この先もお嬢であることだけは、確かです。 |