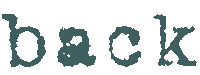曇りのち、雨のち
|
お隣のケンちゃんが真に恐れるものとは、何を隠そう雲である。 あたしがそう告げると、「ぼくもきらいだよ。特に、足がうんと長いやつがね」と仲間を見つけたうれしさを顔ににじませるか、「へえ、ずいぶん臆病だなあ。私は好きなくらいだ。やつのつくる巣の、美しいこと!」と小馬鹿にした眼で見てくるか、大概の人がこのどちらかに属する。 はっきり言おう。変換ミスではけしてない。ケンちゃんが恐れるものは、蜘蛛ではなく、雲なのだ。 お隣のケンちゃんは、一見女の子のような風貌ながら、五十メートル走はクラスで一番で、運動会の徒競走では白いテープを切らなかったことなど一度もない。半ズボンから突き出た足は、そこらの女子より白かったが、そのおみ足をぴっぴっと動かして彼は実に見事に走る。 小学四年生になったというのに、いまだグリンピースを選り分ける癖がぬけないあたしとは大違い、ケンちゃんが給食を残している姿を見たものは誰もいない。一昨日あたしの家で一緒に夕飯を食べた時だって、豚肉とともに炒められたゴオヤアなどという得体の知れないものをケンちゃんはぱくぱくと平らげたのだ。ケンちゃんが我が家でごはんを食べるのはさほど珍しいことではなくなっていて、近頃うちのお母さんはピーマンだとか、シイタケだとかを積極的に皿の上に登場させる。そうして「ケンちゃんはあんなにおいしそうに食べているじゃない」とこれ見よがしのせりふを吐くのだ。前はケンちゃんがやってくるというだけで、それハンバーグだ、やれちらしずしだと、輝かしい面々があたしの拍手とともにテーブルに躍り出ていたというのに! おかげで最近あたしは、ケンちゃんとごはんを食べるのがあまり好きではない。給食の時間でさえ、カレーライスに混入されたグリンピースをあたしがちまちまと取り除いているのを眼にするや否や、ケンちゃんはきっぱりとした声で申すのだ。 「やよいちゃんは偏食が過ぎていけない」 ヘンショクって何よ、とあたしは返して作業を続けるのだ。言っておくが、あたしのは癖なのだ。グリンピース嫌いは小学校三年生という名を返上したときにともにおさらばした。まるっとした緑色をスプーンですくっては空になった別の皿に移動させるのは、利き手の右腕に残った悲しい癖。食べようと思ったら食べられないことはないのだ。主張するあたしに、ケンちゃんは変な顔をする。こないだお父さんに聞いたが、それは渋い顔、というのだそうだ。 ついでにケンちゃんの通信簿の話をしてもよいのだが、それはここでは割愛しよう。比較対象とされるあたしの通信簿に対する思いやりだと察してほしい。 簡単に言えば、ケンちゃんはおばさま方の言う「よくできたお子さんねえ」というやつなのである。だが、「よくできたお子」であるケンちゃんにも、大の苦手としているものが存在し、それが冒頭で述べた通り、雲なのである。 ケンちゃんはただのケンちゃんでなく、お隣のケンちゃんなので、あたしたちは学校へ行くのも帰るのもいつも一緒だ。晴れの日のケンちゃんは、わりあい元気だ。空をちらりと睨み上げ、そこに浮かぶ白いものが小さければ小さいほど、大きな声で「いまいましいやつ!」と吐き出す。このときは、「犬と猿」と同じ意味で「雲とケンちゃん」と言ってもいいかもしれない。もっとも、雲がケンちゃんをどう思っているか知らないが。 空の半分をやつが占拠すると、ケンちゃんはもうだめだ。顔を上げることもかなわず、学校指定の黄色い野球帽をきゅっと目深にかぶり、玄関を出るや否や駆け出していく。「待ってよお」とあたしが声を張り上げてもききっこない。あたしはランドセルをがしゃがしゃ言わせてついていくだけだ。もっとも、ケンちゃんはクラスで一番はやいので、差は開いていく一方だ。運がよければ信号で足止めされているケンちゃんに追いつくことができるが、肩ではあはあ息をさせるあたしの隣で、ケンちゃんはとことこ足踏みをしている。ケンちゃんは信号を無視するということはないが、緑色が灯れば左右の確認もせずにぴゅっと再び走り出す。そうしてあたしは息をぜいはあ言わせ、もはや「待ってよお」と叫ぶ元気もなく、てろてろとケンちゃんの背中を追っかけてゆくのである。帰りもしかり。 それでいくと、あたしとしては雨の日の方が体力的にはずっと楽だ。ケンちゃんは長靴に雨合羽、さらにいかなる季節もゴム手袋を忘れず、黄色い雨傘を差して、水たまりを極力はねないようにしずしずと歩く。風が強く、傘を差していても雨粒が顔にふきつける日など、ケンちゃんは泣き出しそうに眉を下げ、それでもしずしず、しずしず、と学校、もしくは家を目指す。 ケンちゃんは雨が嫌いだが、それは雲が嫌いなせいだ。やつが溶けて落ちてくる、というのはケンちゃんの言。ケンちゃんはあたしのことも実に心配そうな目で見るので、ケンちゃんを安心させるためにいつからかあたしも雨合羽を着て傘を差すようになった。長靴は気分によってははかないし、ゴム手袋はごわごわするためつけないので、ケンちゃんは不満に思っているだろうけれど。 運動でケンちゃんにとても勝てず、通信簿だってあたしとどっこいどっこいのクラスの一部の男子は、雨の日はここぞとばかりにケンちゃんをばかにする。さあ、そうなるとあたしの出番だ。適当に言い返して、ときにはげんこつのひとつでもお見舞いする。都合のいいことに、やつらにはポリシーとかいうものがあるらしく、女のあたしに殴られたことは誰にも言わない。ただ、去り際に「女に守られて、ばっかみてえ」と吐き捨てていく。ちなみにケンちゃんはしずしず歩くのに夢中で、やつらの言葉はこのときひとつも耳に入ってはいない。ただ、あたしが追い払っていることは知っているらしく、時折小さな声でありがとうとつぶやく。 「ケンちゃん、いったい雲の何が怖いのさあ」 「そういうやよいちゃんは、どうして梅ゼリーの梅を残すの」 めざといケンちゃんは、あたしの皿をスプーンで指して言った。日曜日で、外は雨だった。雨の日、よほどの用事がない限りケンちゃんは外に出ないので、あたしが出向いてやらなくちゃならない。ケンちゃんのお母さんは、毎度おやつを出してくれるが、正直今日の選択はいただけない。出すなら果実の入っていないやつがいい。 「雲なんて、空にいるだけだよ。あたしたちに何もしてこないよ」 「見ているだけで、おぞけ立つよ」 視界に入ったわけでもないのに、そう口に出してケンちゃんは肩をぶるりと震わせた。ケンちゃんの部屋は、いつの日もぴったりとカーテンが閉じられているので、外の様子はわからない。おそらくまだ降っているだろうけれど、今日の雨は霧雨なので音は聞こえなかった。 「やつらは集合して、合体してひとつになって、溶けてぼくらを襲うんだ。そう、今、まさに! そして明日にもなれば、まだ水たまりがあちこちに光っているというのに、また空でぼくらを襲う準備を着々と始めるんだ。ああ恐ろしい」 「雨に当たっても別に痛くもないし、ただれもしないよ。寒いときは冷たいけれど、大丈夫だよ」 何度も言ったことのあることをあたしが口にすると、ケンちゃんはこの日も、「たっしていないからだ」と真面目な口ぶりで言った。 「今は大丈夫でも、雨が当たったことを、体は覚えているんだ。ずっと浴び続けて、いつか、限界を超えてしまうんだ」 限界を超えたらどうなるのか、ケンちゃんは言わなかった。ただ、この世で一番恐れるべきものだとでもいうように、左右に頭を振っていた。 「でもケンちゃん、雨が降らないと稲は育たないし、あたしたちの飲む水ももともとは雨だよ」 「ぼくは豚の死ぬところを見たくない」 唐突にケンちゃんは言った。 「だけど、とんかつは好きなんだ」 ケンちゃんはあたしの皿を引き寄せると、あたしの食べなかった梅の実を食べた。あたしはケンちゃんのこういうところは好きだ。 ケンちゃんは雲が嫌いというだけで、外で遊ぶのが嫌いなわけではない。よって、ケンちゃんがもっとも嫌がるのは、梅雨ではない。 ケンちゃんもあたしもまだ小学四年生だ。生まれてからの年数が二桁になったかならないかのあたしたちが、夏の日、我を忘れて夢中で遊んでいても、それは仕方がないというものだ。汗みずくになったケンちゃんが、はっと気がついた頃には遅かった。山の向こうに頭をちょっぴり覗かせていただけの入道雲は、いつのまにか巨人に大進化をとげていて、柔和な白い顔をどす黒く変化させてあたしたちを見下ろしていたのだった。 ケンちゃんはポケットに小銭を突っ込んでくることはあっても、遊ぶときに折り畳み傘を持ってくるような、そんな野暮なことはしない男の子なのである。 「やよいちゃん、逃げるよ!」 勇ましく言ったケンちゃんは、だけどあたしに手を差し伸べることもなく駆け出した。急いであたしもジャングルジムを降りると、ケンちゃんの後を追った。 追いながら、振り返り、ああだめだこれはつかまってしまう、とあたしは直感した。長い滑り台に心惹かれて、いつもは来ない、家から離れた公園に来ていたのだ。あたしは叫んだ。 「ケンちゃん、そこの角、右に曲がって。竹じいのところに行こう」 左に曲がろうとしていたケンちゃんは、たたらを踏んで振り返った。ケンちゃんは竹じいを知らず、あたしも正直気は進まないのだが、仕方がない。あたしはケンちゃんの手を引っ張ると、右へ導いた。 あたしのおじいちゃんは二人ともまだ元気で、お母さんの父親は梅吉といい、あたしたちと一緒に暮らしている。梅じいのお父さんは、竹造といって、あたしから見るとひいじいちゃんだ。あたしが目指したのは、その竹造じいちゃん、竹じいのところだった。 なんとか巨人につかまることなく竹じいの家に辿り着いたあたしたちは、縁側から靴を脱いで上がった。無用心な竹じいが、玄関の鍵を開けっ放しにしてあるのは知っていたが、竹じいが縁側に座っているのが見えたので、そちらに転がり込んだのだ。 「さわがしいなあ」 にやりと竹じいは笑い、うちわをぱたぱたとさせていた。 ひいばあちゃんはあたしが生まれる前に死んでしまっていた。梅じいはあたしたちと一緒に暮らしているというのに、竹じいは一緒に暮らそうというお母さんの申し出を頑として受けず、ここで一人で住んでいた。断り文句はいつも同じ、「お前はわしの楽しい余生を邪魔する気か」である。「お前らと暮らして、何が楽しいんじゃ」というのは、竹じいの口癖と言ってもいいくらいで、あたしも何度も耳にしている。ただ、「一緒に暮らす気はさらさらないが、やよいはできるだけ遊びに来なさい」と言うのも竹じいで、お母さんは「まったく変なひとなんだから」とよくぶつぶつ言っている。 お母さんがそう言ったからというだけではないのだが、あたしは竹じいが少し薄気味悪かった。遊びに来れば黄ばんだ歯を見せてにんまり笑う竹じいは、びっくりするほどしわくちゃで、しゃべるたびに一緒に動くしわは、竹じいが顔に飼っている虫か何かに見えてくる。「できるだけ遊びに来なさい」と言われていたあたしだけども、ひとりでそうする気にはとてもなれなかった。あたしにはケンちゃんというお隣さんがいたが、二人で竹じいを訪ねたところで楽しいことが起きそうな予感はつゆほどもない。お母さんと一緒に来たときも、おやつにでるのは仏壇の芋ようかんがほとんどだ。あれは喉につまるのであまりよろしくない。 こういった理由で、あたしが自分で竹じいのところに来たのはこの日が初めてだったし、ケンちゃんが竹じいに会ったのも初めてだった。竹じいは縁側で四つんばいになって息を整えているケンちゃんを見て、「ほお、ぼうずか」と言った。よくあることだが、ケンちゃんを女の子だと思っていたようだ。 「やよい、今日はどうした。ガキ大将にでも追っかけられたか」 珍しくやってきたあたしを見て、竹じいは嬉しそうだった。あたしは首を振った。 「夕立が来そうだったから」 「逃げてきたのか」 竹じいはまたにやっと笑った。縁側に近い部屋は、蛍光灯が灯っていて、竹じいは背後の光に不気味に照らされていた。あたしはぞおっとした。 「わしは待っていた」 一瞬、あたしを待っていたのかと思い、あたしはさらに身をふるわせたが、それは間違いであることを直後に知った。ぽつり、ぽつりと大粒の雨が、竹じいの庭に生えた朝顔の葉を打った。間を置かず、雨粒は空から勢いよく降りてくると、あちらこちらでばちばちと跳ねてめちゃくちゃなコーラスを奏で出した。予想以上の音に目をむいたあたしは、隣ですっくと立ち上がった竹じいが「ひゃっほー」と奇声をあげて縁側から飛び出したのを見て、さらに目を開かなければならなかった。 裸足で庭に降り立った竹じいは、そこでくるくると踊りだした。 横になっていたケンちゃんはびっくりして跳ね起きると、やめてくださいと先生に言うようにかしこまった言葉で竹じいに呼びかけた。竹じいは手も足も止めることはなかった。 「何を恐れる」 あれは、盆踊りだろうか。ケンちゃんは、しばらく、竹じいを白い顔で見つめていた。放心しているようにも見えた。台風で傘がおちょこになり雨にまみれるサラリーマンを見たことはあっても、傘を持っておらずかばんを頭の上に乗せて走る女子中学生を見たことはあっても、夕立を待っていたと言って雨の中で踊りだすじいさんを見たことは、ケンちゃんにはなかったのだ。もちろんあたしも、まさか竹じいにこんな趣味があるとは思っていなかった。 「やよい、お前も来い」 竹じいに呼ばれ、あたしは「えっ」と肩を跳ね上げた。 「あのう、竹じい、傘も差さずに?」 「きもちいいぞ、来い」 あたしは縁側にじっと正座したまま動かなかった。なんとなくケンちゃんの顔を見ることができず、竹じいのわけのわからない踊りを見つめていた。 「ぼうず、お前も来い」 まさか自分も呼ばれるとは思っていなかったケンちゃんは、続いて「えっ」と肩をびくつかせた。 ケンちゃんが隣で、そわそわしているのに気がついたあたしは、そっとケンちゃんを見た。おや、と思う。ケンちゃんの頬は、先ほどのように青ざめてはいなかったのだ。 「やよいちゃん、あれ、おじいちゃん?」 「ひいじいちゃん。竹じい」 ケンちゃんの問いかけに、あたしは答えた。 「竹じい、いくつ?」 「こないだ九十のお祝いしたよ」 ふうん、とケンちゃんは言った。 「九十か」 このときのケンちゃんを見ていると、言っても許される気がして、あたしは口に出してみた。 「なんだか、おもしろそうじゃない?」 頭で、肩で、雨粒をダンスさせながら、自分も骨ばった手をひらりひらりとさせている竹じい。竹じいから眼をそらさないまま、ケンちゃんは小さくうなずいた。 そうなるとあたしは一番偉い人から許可をもらった気になって、ケンちゃんに何も告げずに庭に飛び出した。雲嫌いのゆえに雨嫌いなケンちゃんが、おもしろそうだというあたしの言葉に賛同をしめしたならば、いったい誰に止められよう! どこぞの王様だって無理である。あたしは竹じいの真似をして、水のたまりだした庭を裸足で駆けて竹じいの踊りに加わった。足をばたばたさせれば、ゆるくなった土が舞い上がり、あたしの頬まで飛んできた。 「やよいちゃん」 ケンちゃんがかぼそい声で呼んだのがわかったが、あたしはもうそちらには戻れなかった。忘れかけている去年の運動会のダンスを踊りながら、あたしは言った。 「ケンちゃんもおいで!」 「ぼうずも来い!」 竹じいも言った。 にこにこ笑うあたしと、にやにや笑う竹じいに誘われて、ケンちゃんはそろりと縁側から、乾いた土に足を降ろした。脱ぎ捨てた靴に歩み寄ろうとするケンちゃんに、竹じいが「いらん、いらん」と呼びかけた。 「裸足で来い、裸足で来い」 ケンちゃんは、あたしたちをじっとにらんだかと思うと、覚悟を決めたようで、えいやと夕立の中にジャンプした。 しかし、ケンちゃんはどうしてもケンちゃんだった。ばちばちと雨が当たったとたん、ぎゃっと叫んでまた縁側へと逃げ帰ってしまった。 「なんなんだ、あのぼうず」 きょとんとして踊りをやめた竹じいを、あたしは見上げた。強い夕立でかすむ竹じいは、いつもより怖くなく感じられて、あたしは竹じいに告げた。 「ケンちゃんは、空の雲が怖くて、雨が怖いの」 きちんと、蜘蛛ではなく雲だとわかるように。 「ははあ」 竹じいはまたもやにやりと笑ったようだった。雲と雨が怖いとわかっただけで、何がそんなに納得できるのかわからなかったが、竹じいはもうあたしの説明を必要としていないようだった。 「ぼうず、来い!」 なおも竹じいは叫んだ。縁側にしがみつき、ケンちゃんはぶるぶると震えて「いやだ」と言った。 「何を怯える。竹じいは元気だぞ!」 ケンちゃんのふるえがわずかに止まった気がして、あたしも叫んだ。 「あたしも元気だよ!」 ケンちゃんは、夕立に向けていた背を、縁側にぴたりと押し付けた。そうして、顔を下に向け、勢いよくあたしたちのところへ駆けてきた。 風が飛び込んできた、と思った。あたしは一瞬動けなかったが、竹じいは細い腕でケンちゃんを受け止めると、そのまま持ち上げてくるくる回った。竜巻になった竹じいとケンちゃんを見て、あたしは嬉しくなってぴょんぴょん跳ねた。 竹じいはケンちゃんを降ろすと、また腕と足をひらひらさせて踊りだした。あたしも、竹じいに続く。ケンちゃんは、固く眼をつぶり、がたがたと震えながらも手と足を闇雲に動かしていた。 「もっと軽快にやれ、ぼうず」 とても踊りには見えないケンちゃんの動きに、笑いながら竹じいが言った。それでもケンちゃんは、顔をしかめたままばたばたしている。しきりに何かをつぶやいているので、耳を寄せてみると、「竹じいは九十歳、竹じいは九十歳」と唱えているのだった。それがずいぶんすてきな響きに思えたので、あたしも声を上げた。 「竹じいは九十歳! 竹じいは九十歳!」 竹じいも怒鳴った。 「竹じいは九十歳! 竹じいは九十歳!」 ケンちゃんが、世界の終わりだとでもいうような声で叫んだ。 「竹じいは九十歳! 竹じいは九十歳!」 最後の馬力か、強さを増した夕立の中で、あたしたち三人は踊りながら声を張り上げた。 その晩、ケンちゃんは熱を出した。 雨が止んでから、あたしたちは竹じいに借りたバスタオルで体をくるんで、てるてるぼうずのような格好で家に帰った。あたしは家に入るやいなや即刻あたたかいお風呂に入れられたし、ケンちゃんもそうだったと聞いたが、夕ご飯も食べないうちからケンちゃんはくにゃりと倒れてしまったそうだ。 あたしから事情を聞いたうちのお母さんは、次の日あたしを引き連れて竹じいのところに行った。言葉はやわらかくしてあったが、お母さんが言ったのは、つまるところ「変な遊びをおしえるな」という内容だった。お母さんの文句をあの、にやにや笑いで受け止める竹じいは、ケンちゃんが熱を出したと聞いても「最近の子どもは弱くていかん」などということは言わなかった。 「熱を出したか、それはけっこう! そうやって子どもは強くなるんじゃ」 けっこうだなんて不謹慎だとお母さんは不満げだったが、あたしは竹じいが前ほど苦手ではなくなった。 帰るとき、あたしはこっそり言った。 「また来るよ、竹じい」 「おお、来い。ぼうずも連れて来い。芋ようかん食わせてやる」 こっそり返した竹じいに、これは言っておかねばなるまいとあたしはさらにこっそり付け足した。 「喉がつまるから、麦茶、用意しておいて。あたし、緑茶、苦くてだめなの」 芋ようかんの味自体は嫌いではないのだ。これでおそらく、竹じいの家でまでケンちゃんに「ヘンショクが過ぎていけない」なんて言われることもない。 お昼のそうめんを食べた後、あたしはケンちゃんのお見舞いに出かけた。ケンちゃんは布団の中で、ふうふう言いながら横になっていたけれど、あたしの顔を見ると手招きをした。 「やよいちゃん、ぼく、考えたんだ」 ケンちゃんの頭の近くに腰掛けて、あたしは尋ねた。 「何を?」 「やっぱり、雨合羽は着るべきだよ。熱を出さないためにも」 あたしは何も言わず、ただ首を傾げてみせた。ケンちゃんはあたしを見て少し笑った。なんだか、竹じいみたいな笑い方だった。 「ケンちゃん、夕立の降りそうな日にまた行こうね。竹じい、芋ようかんごちそうしてくれるって」 熱が出て赤くなった顔で、ケンちゃんは「うん」と言った。 カーテンの開かれた窓の向こうでは、小さな雲が一切れ、呑気に空に浮かんでいる。 |